FIT(固定価格買取制度)とは? 成果や仕組み、メリット・デメリットを解説!
投稿日:2022/11/16
更新日:2024/03/29

でんきの豆知識
日本はエネルギーに関する課題の多い国です。火力発電大国でありながら、エネルギーの自給率は低く、燃料調達のほとんどを諸外国からの輸入に頼っています。近年は世界情勢が不安定になっており、いつまでも安定的に燃料を輸入し続けられるとは限りません。また2022年のように、燃料価格が高騰する可能性もあります。さらに、化石燃料には枯渇の問題や、発電時にCO₂を排出するため、地球温暖化を進行させるという問題もあります。
そこで近年注目されているのが、再生可能エネルギーです。日本には、再生可能エネルギーの普及を推進するための「FIT(フィット)」と呼ばれる制度があります。
本記事では、FITの概要や仕組みについて解説します。FITの対象である太陽光発電を導入するメリットやデメリットもご紹介するので、一般住宅への太陽光発電設備の設置をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事の内容は2024年3月25日時点の情報です
この記事を書いた人

- マーケティング室 室長
-
大学在学中、発展途上国でのボランティア活動がきっかけで
伊藤忠エネクスに入社。
入社後は一貫して電力ビジネスに携わり、電力ビジネス領域における大規模システム構築を実現。
電力のスペシャリストとして電力ビジネスの拡大に尽力している。
この人が書いた他の記事
目次
FIT(固定価格買取制度)とは?
FITは「Feed-in Tariff(フィードインタリフ)」の略称で、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と訳されます。
電力会社はFITにより、再生可能エネルギーから作られた電気を、政府が設定した固定価格で一定期間にわたり買い取ることが義務付けられています。なおFITの買取価格は、毎年、調達価格等算定委員会の意見を尊重して、経済産業大臣が決定します。
FITは1991年にドイツで、1992年にスペインで導入され、日本では2009年11月より、前身となる「太陽光発電余剰電力買取制度」が導入されました。2012年7月から「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)」と名前を変え、太陽光発電以外の再生可能エネルギーも対象となり、また余剰電力買取から全量買取へと変更されました。(10kW未満の太陽光発電は、現在も余剰買取。)
FIT(固定価格買取制度)の対象となる再生可能エネルギー
FITの対象となるのは太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電の5つです。
太陽光発電
太陽光発電は太陽の光を電気に変換する発電方法です。太陽の光がソーラーパネルに取り付けられた太陽電池(半導体素子)に当たることで電気が作り出されます。建物の屋根や壁などにソーラーパネルを設置すれば発電できるため地域的な制限がなく、送電設備のない山岳地帯でも活用できますが、天候によっては十分に発電できない点が課題です。
風力発電
風力発電は風の力を電気に変換する発電方法です。風の力を利用して「ブレード」と呼ばれる巨大な羽を回転させ、そのエネルギーで発電します。風さえあれば夜間でも発電でき、大規模な設備なら火力発電と同程度まで発電コストを抑えられます。ただし、陸上に風車を設置するには広い土地が必要で、かつ、常に一定以上の強さの風が吹いていないといけません。国内では風力発電の条件に合う土地が、北海道や東北といった一部地域に限られている点が課題です。
水力発電
水力発電は水の持つ位置エネルギーを電気に変換する発電方法です。水が高い場所から低い場所へ落ちる際のエネルギーを利用して水車を回転させ、発電します。発電コストが安価で、エネルギー変換効率も高い点がメリットですが、ダムの建設には多くの時間と巨額の初期投資が必要な点が課題です。
地熱発電
地熱発電は地中に存在する高温の水や水蒸気の力を電気に変換する方法です。地下から取り出した蒸気でタービンを回転させ、発電します。火山国である日本には、豊富な地熱エネルギーが存在しています。出力が安定しており24時間発電できますが、設備の開発が長期にわたり、開発費用が高い点が課題です。
バイオマス発電
バイオマス発電では、バイオマスと呼ばれる動植物から生まれた化石燃料以外の生物資源を発電に利用します。木質資源、食品廃棄物、家畜糞尿、下水汚泥などを燃焼、あるいは、ガス化することで発生する水蒸気やガスでタービンを回転させ、発電します。廃棄物を利用するため資源の有効活用につながる一方、資源そのものの安定供給が難しい点が課題です。また資源の調達や運搬、管理にコストがかかるため、発電コストが高い点も課題として挙げられます。
FIT電気と再生可能エネルギー(非FIT電気)の違い

そもそも再生可能エネルギーとは、資源が枯渇せず永続的に利用できる自然由来のエネルギーのことで、発電時に温室効果ガスを排出せず、また国内で調達・生産できる、重要な国産のエネルギーです。前述したFITの対象となる5種類の他、太陽熱、雪氷熱、温度差熱、地中熱なども、再生可能エネルギーに含まれます。
再生可能エネルギーによって発電された電気のうち、FITで買い取られた電気のみがFIT電気となります。再生可能エネルギー由来の電気には、FIT電気と非FIT電気がありますが、その扱いは大きく異なります。
本来、再生可能エネルギーで発電された電気は、「電気そのものの価値」の他に、二酸化炭素を排出せずに発電されたという「環境価値」を持っています。逆にいえば、この環境価値を持っていなければ、100%再生可能エネルギーとは認められません。非FIT電気は環境価値を持っているため、紛れもない100%再生可能エネルギーです。
FIT電気の買取費用は、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)という形で、国民が負担しています。この再エネ賦課金は電気の環境価値に対して支払われており、FITで買い取られる電気がもともと持っていた環境価値は、国民に帰属します。FIT電気は「環境価値」を失うため、再生可能エネルギー由来の電気でありながら、100%再生可能エネルギーとは認められないのです。
FIT(固定価格買取制度)が導入された背景・目的
FIT(固定価格買取制度)が導入された背景には、日本のエネルギー自給率の低さがあります。
日本は世界有数のエネルギー消費国でありながら、エネルギー自給率は2020年時点で11.3%、先進国の中でも37位と極めて低いです。火力発電には石油や石炭、天然ガス(LNG)などの化石燃料が必要で、日本はそのほとんどを輸入に頼っています。
化石燃料には限りがあるため、利用し続ければいずれは枯渇するでしょう。また化石燃料を燃やすとCO₂が発生するため、地球温暖化を進行させることにつながります。さらに、国際情勢の変化によって安定的に輸入ができなくなったり、輸入価格が高騰したりといったことも起こり得ます。
そこで注目されているのが再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーによる発電なら、化石燃料の輸入は必要なく、CO₂の排出も抑えられます。しかし、再生可能エネルギーによる発電には、新たな設備の購入やそれらを維持する費用がかかるため、導入に踏み切りにくいと感じる企業や一般家庭も少なくありません。FITはこういった費用負担を軽減させ、再生可能エネルギーによる発電を普及させるために導入されました。
FIT(固定価格買取制度)の成果

FITの前身である「太陽光発電余剰電力買取制度」が導入された2009年以降、再生可能エネルギーの供給量は大きく伸びています。日本の再生可能エネルギーの供給量は、2010年度は水力を含めて7.7%でしたが、2021年度には13.3%にまで増えています。
内訳を見ると割合が大きく増えているのは太陽光発電です。FITは日本の再生可能エネルギーの普及、とりわけ太陽光発電の普及で一定の成果を発揮しているといえます。
日本のエネルギー確保において一定の成果を上げているFITですが、一方で課題も生じています。再生可能エネルギーによる発電は火力発電などとは異なり、天候などの条件によって発電量が変動し、また需要が増えたときに発電量を増やしたり、需要が減ったときに発電量を減らしたりといったことがほとんどできません。供給量をコントロールできない電力の割合が増えたことで、需給バランスの調整が難しくなっている点は、再生可能エネルギーの供給量が増えたことによる課題といえるでしょう。
FIT(固定価格買取制度)の仕組み

ここからは、FITの仕組みについて改めて詳しく解説します。
FITでは、企業や一般家庭が再生可能エネルギーによって発電した電気を、電力会社が一定期間、固定価格で買い取ること約束しています。買い取りの対象となるのは、先述した5つの再生可能エネルギーによって発電された電気です。
再生可能エネルギーによって作られた電気は、まずパワーコンディショナーに取り込まれ、直流電力からビルや住宅などで利用できる交流電力に変換されます。全量売電の場合は、変換された全ての電気が送電線を介して電力会社へ送られ、余剰売電の場合は、自家消費して余った分の電気が送電線を介して電力会社へ送られます。送電された電力が電力会社によって固定価格で買い取られ、買取費用が支払われる仕組みです。
なお、先述したとおり、電力会社がFITで再生可能エネルギー由来の電力を買い取る際に要する費用の一部は、再エネ賦課金によって賄われています。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)とは?
再エネ賦課金についても、改めて確認しておきましょう。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、再生可能エネルギーの普及のために、電気を使用する全ての企業や家庭から集められている費用です。毎月の電気料金と併せて、電力使用量に応じた金額が徴収されます。つまり、電気を使用する全ての人がFITを支えているのです。再エネ賦課金によってFITの買取価格が高めに設定されていることで、企業や一般家庭が再生可能エネルギーによる発電を始める際の初期コストの回収が容易になっています。
再エネ賦課金は年度の開始前に、再エネ特措法で定められた算定方法に則り、経済産業大臣が設定します。
FIT(固定価格買取制度)による10kW未満の太陽光発電の買取価格の推移

ここからは、一般住宅向けの10kW以下の太陽光発電に限定して解説していきます。
2014年度から2025年度までの、10kWh以下の太陽光発電の買取価格は、以下のとおりです。
【10kW未満の太陽光発電の買取価格】
| 年度 | 買取価格(/kWh) |
|---|---|
| 2014年度 | 37円 |
| 2015年度 | 35円 (33円 ※出力抑制対応義務なし) |
| 2016年度 | 33円 (31円 ※出力抑制対応義務なし) |
| 2017年度 | 30円 (28円 ※出力抑制対応義務なし) |
| 2018年度 | 28円 (26円 ※出力抑制対応義務なし) |
| 2019年度 | 26円 (24円 ※出力抑制対応義務なし) |
| 2020年度 | 21円 |
| 2021年度 | 19円 |
| 2022年度 | 17円 |
| 2023年度 | 16円 |
| 2024年度 | 16円 |
| 2025年度 | 15円 |
表を見ると分かるように、買取価格は年々下落しています。10kW未満の太陽光発電は主に一般住宅向けであり、FITによって一般住宅への太陽光発電設備の設置が増えた結果、設備費用や工事費用といった導入コストが安くなったことが主な理由です。買取価格は下がったものの、導入コストも下がったため、初期費用の回収期間はFIT制度の導入当初と大きく変わらないでしょう。
FIT(固定価格買取制度)の対象となる太陽光発電を導入するメリット

一般住宅でFITの対象となる太陽光発電を導入する主なメリットは、以下の3つです。
- 売電収入を得られる
- 自家消費によって電気料金が安くなる
- 災害対策になる
それぞれ解説します。
売電収入を得られる
太陽光発電設備を導入すると、売電収入を得られる点が第一のメリットです。特にFITの適用期間中は電気の買取単価が高く、また10kW未満の太陽光発電は、10年間は買取単価が固定されているため、安定的に売電収入を得られるでしょう。
FITにおける2024年度の10kW未満の太陽光発電の買取価格は、16円/kWhです。1年間に3,000kWhの電気を売電すると仮定した場合、売電収入は48,000円となります。
自家消費によって電気料金が安くなる
再生可能エネルギーで作った電気は、売電だけでなく自家消費にも利用できます。太陽光発電で作った電気を自家消費に回せば、その分電力会社から電気を購入せずに済み、電気料金が安くなるでしょう。
一般住宅なら発電量によっては、日中の消費電力をすべて自家消費で賄えるでしょう。また蓄電池を組み合わせれば、日中だけでなく夜間も太陽光発電で作った電気を使用できます。
近年は国際情勢の変化や円安の影響などにより、電気料金が高騰しています。これから太陽光発電を導入する場合、FITの買取価格よりも電気料金の単価の方が高くなる可能性が圧倒的に高いため、自家消費のメリットは大きいです。
先述した通り、FITにおける2024年度の10kW未満の太陽光発電の買取価格は16円/kWhですが、東京電力エナジーパートナーの電気料金は、従量電灯Bで第1段階料金が29.80円/kWh、第2段階料金が36.40円/kWh、第3段階料金が40.49円/kWhとなっています。売電よりも自家消費の方がお得というのは明らかです。
災害対策になる
自宅で再生可能エネルギーを用いて発電できるようにしておくことは、有効な災害対策となります。
現代の生活には電気が欠かせませんが、大規模な災害時は停電が起こるケースも珍しくなく、復旧までに時間がかかることも多いです。2〜3週間と長期にわたって電気が使えなくなった事例もあります。
太陽光発電設備がある住宅なら、万が一停電しても、発電して電気を使用できます。冷蔵庫や洗濯機などの電化製品を電気の復旧前から使用でき、災害前に近しい、比較的便利な生活ができるでしょう。
ただし太陽光発電は、晴れ〜曇りの日の日中しか発電できません。蓄電池を設置しておけば、太陽光発電で作った電気を蓄えられるため、夜間や天候不良の際にも電気を使用できます。太陽光発電によるメリットをさらに生かすなら、やはり蓄電池も併せて導入するのがおすすめです。
FIT(固定価格買取制度)の対象となる太陽光発電を導入するデメリット

FITの対象となる太陽光発電の導入には、知っておきたいデメリットもあります。主なデメリットは、以下のとおりです。
- 初期導入コストがかかる
- 定期的なメンテナンスが必要
- 卒FIT後は売電価格が下がる
それぞれ解説します。
初期導入コストがかかる
先述したとおり、10kW未満の太陽光発電の導入コストは安くなっていますが、とはいえ、ある程度まとまったお金は必要です。例えば、住宅用太陽光発電の新築設置にかかった費用は、2022年度は平均で26.9万円/kW、2023年度は平均で28.8万円/kWです。内訳はソーラーパネルやパワーコンディショナーなどの設備費が約79%、工事費が約21%です。
売電収入や電気料金の節約額、また後述する定期メンテナンスの費用なども踏まえて中長期的なコストメリットを計算し、本当に導入すべきかどうかよく検討しましょう。なお、蓄電池も併せて導入する場合は、もちろんその分の費用も上乗せされます。蓄電池は、電気を蓄えられる容量が大きければ大きいほど価格が高くなる傾向にあるので、日常生活や災害時の備えに必要な容量をしっかりと見極めてから購入しましょう。また自治体によっては、太陽光発電設備や蓄電池の設置に対しての補助金を設けているところもあります。導入の際には、活用できるものがないか確認してみてください。
※参考:経済産業省 . 「太陽光発電について」 .https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/091_01_00.pdf , (2023年12月) .
定期的なメンテナンスが必要
太陽光発電設備を設置したら、定期的なメンテナンスが必要です。例えば、ソーラーパネルは屋外に設置されるため、台風をはじめとする自然災害が発生した際に破損するリスクがあります。また故障はしていなくても、風雨によってパネルにほこりや汚れが蓄積し、発電効率が低下することもあります。定期的な点検で、不具合の早期発見を心がけることが大切です。
太陽光発電に関連したメンテナンスの中には、電気工事や電気設備の点検など、有資格者にしか行えない作業が含まれる場合があります。資格が必要なメンテナンスについては、設置を依頼した業者に確認しておきましょう。
卒FIT後は売電価格が下がる
卒FITとはFITの適用期間が満了し、電気の買い取りに固定価格が適用されなくなることです。卒FIT後はFITの適用期間中と比べて、買取価格が下がります。参考として2013年のFITの売電価格と、現在のエリア電力会社の買取価格を表にまとめました。
【卒FIT後の買取価格】
| エリア電力会社 | 買取単価(/kWh) | 2013年のFITの売電価格(/kWh) |
|---|---|---|
| 東京電力 | 8.5円 | 38円 |
| 北海道電力 | 8円 | |
| 東北電力 | 9円 | |
| 中部電力 | 7円 | |
| 北陸電力 | 8円 | |
| 関西電力 | 8円 | |
| 中国電力 | 7.15円 | |
| 四国電力 | 7円 | |
| 九州電力 | 7円 | |
| 沖縄電力 | 7.7円 |
2013年のFITの売電価格と比較して、現在のエリア電力会社による買取価格は大幅に低いことが見て取れます。
FITの適用期間中の買取価格が高い理由は、先述したとおり、FITで電気を買い取る費用に再エネ賦課金が充てられているためです。卒FIT後は再エネ賦課金の割り当てがなくなり、各買取業者が独自に価格を設定するため、買取価格が下がるのです。
少しでも売電収入を多くしたい場合は、卒FIT後もそのままエリア電力会社への売電を継続するのではなく、より買取単価の高い買取業者に切り替えるのがおすすめです。
※参考:株式会社エネクスライフサービス . 「太陽光電力買取サービス」 .https://afterfit-itcenex.com/ , (2024-03-25) .
まとめ
FITは日本のエネルギー自給率の向上、とりわけ、再生可能エネルギーの普及を促進させる重要な制度です。一般家庭でもFITの対象となる太陽光発電を導入すれば電気料金を節約でき、また災害時の停電への備えにもなります。地球温暖化の防止に貢献したい方はもちろん、高騰している電気料金を削減したい方も、ぜひ、太陽光発電の導入を検討してみてください。
株式会社エネクスライフサービスは、卒FITを迎えた方へ「太陽光電力の買取サービス」を提供しています。高水準の買取価格を実現しており、例えば、関東エリアの買取単価は12.5円/kWhです。さらに、TERASELでんきをご利用の場合は、買取単価が1円アップします。卒FIT後もより多くの売電収入を得たい方は、ぜひ、エネクスライフサービスの「太陽光電力の買取サービス」をご検討ください。
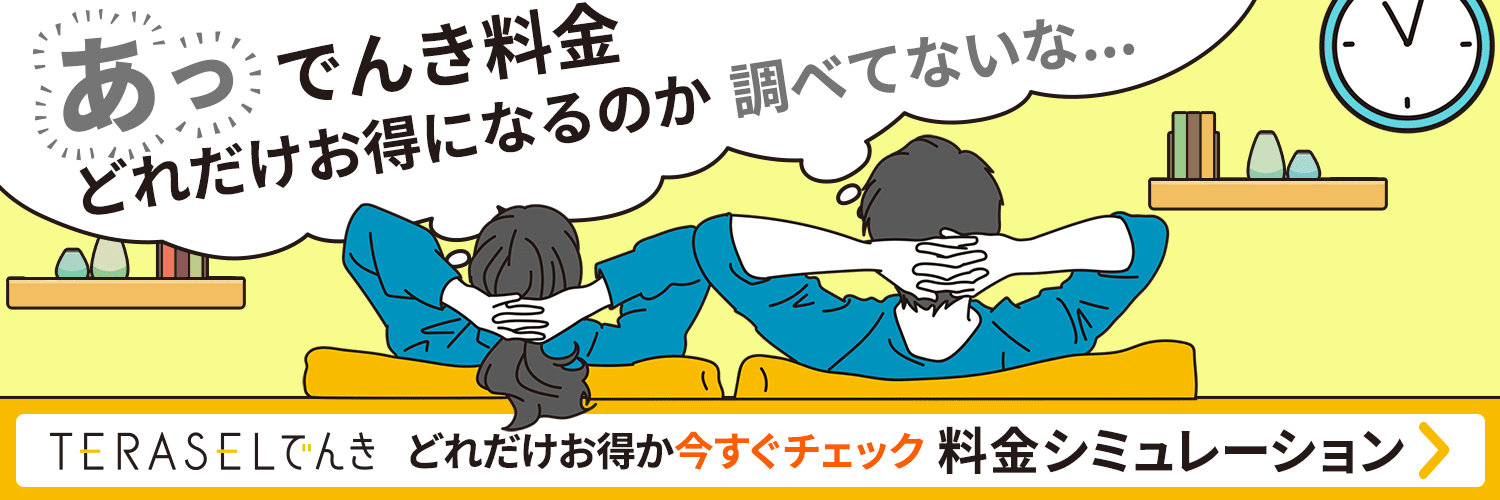
関連記事










